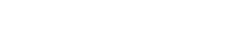グレムリンの話

1984年公開の映画。ジョー・ダンテ監督。
この頃は、SFX(特殊撮影)の映画が多く撮られました。今のCGの映画にはない、魅力に迫りたいと思います。(大袈裟)
ギズモ
当時、父上と見に行きました。
クリスマスに合わせた公開だったと思います。
グレムリンとは、妖精の名前で機械の原因不明の故障は、グレムリンの仕業と考えられていました。
飛行機にまつわる逸話が多くあります。
トワイライトゾーンの “2万フィートの戦慄” にもグレムリンがでてきます。
第二次世界大戦中にイギリス空軍の爆撃機がグレムリンの集団に襲われる事件が本当にあったそうです。
発明家ランダルが息子のクリスマスプレゼントにとチャイナタウンの骨董店で見つけた謎の生き物モグワイ。
ギズモと名付けられます。ギズモとは、SFにでてくる新兵器や007にでてくる秘密兵器のこと。
10ccのメンバーが作ったギズモトロンなる楽器もあります。ギターのサステインを無限に伸ばす装置。よくわからん。
テープに録音した音をキーボードで再生するアナログなシンセサイザーにもギズモと呼ばれるものがあったような?
ランダル氏は、自ら発明した便利グッズを売り歩くセールスマン。ただこの便利グッズ、どれもポンコツばかり。うまく作動しません。

グレムリンに登場するギズモ。かわいい。
こんなの本当にいたら飼いたい。
ただですね、みなさんご存知かと思います。モグワイ飼うのは大変なんです。
三つの約束
モグワイ飼育の際、絶対守らないといけない三つの約束があります。
その一・光に当ててはいけない。強い光を嫌います。特に日光を浴びると死んでしまいます。
その二・水に触れさせない。増えます。
その三・夜中の12時過ぎて食べ物を与えてはいけない。凶暴なグレムリンに変体します。
グレムリン
モグワイと打って変わり爬虫類のようなキモい姿に。昔、原寸大のグレムリンの模型があってめちゃくちゃリアルでした。
下品で醜悪なグレムリンたちですが、ユーモアがありますね。
リーダー格のストライプ。頭も良く、恐ろしい奴です。
グレムリンのビジュアルは、水木しげる先生の妖怪図鑑では、耳の尖ったゴブリンそのもので如何にも妖精といった印象です。
80年代になりSFXや特殊メイクが使われたホラーやSFが増えて、ゾンビやクリーチャーがたくさん作られました。
先述のトワイライトゾーンに登場するグレムリンも醜悪な怪物としてデザインされています。
実在する動物を参考にして作られたグレムリ ン。個体差もあり面白い。続編に登場するモホークが好きです。モグワイの時から目付きが悪い。

見どころ
主人公ビリーのピンチにギズモがラジコンカーに乗って助けにきます。スティングレイですね。
モグワイは、学習能力が高く車の運転もテレビで覚えたようです。結構ノリノリなのがかわいい。
マペットのギズモやグレムリンは、操演者が見切れるようにカメラワークが工夫されています。
一部でアニメーションも使われています。グレムリンの1m程度の体高も撮影しやすいサイズ設定だったのかも。
SFXは、特殊メイクやアニメーション、マットペインティング(ガラスに背景を描いて透明な部分に実写をはめ込む技法)あとゴーモーションシステム(架空の生き物などを専用の装置で操演する機械)などで作られています。

職人たちが知恵を振り絞って動かすギズモたちは、生命力溢れる演技をします。
あとこの映画の1番の魅力は、
フィービー ケイツですよ。

すみません。でもかわいかったなあ。
ホラー映画の魅力は、ヒロイン。可愛い女の子は、大概最後まで生き残ります。
イキってるパンクは、冒頭で死にます。
それな!
騒動のあとギズモは、骨董屋の老人に引き取られていきます。さよならギズモ。
クリスマスって楽しい反面なんだか寂しい気持ちにもなりますよね。
ケイトのお父さんの話とか、切なすぎる。
ゴーストバスターズもリメイクされたしグレムリンもリメイクされたりして。でもオリジナルの良さが色褪せることはないでしょう。
まとめ
ヤムヤム、うまい うまい
-
前の記事

菅野よう子さんを知っておくれ 2020.03.22
-
次の記事

JAZZのはなし 2020.04.06