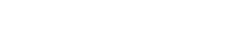ソラニンのこと

前回に引き続き浅野いにお先生のお話。
ソラニン
ソラニンは新装版でもってます。装丁は多摩川土手の写真。この頃の先生の絵は吉本良明先生ぽいですね。”青い車”(吉本良明の漫画)の影響も感じさせます。
夢を捨てきれないバンドマンとその彼女の物語。女性にも人気のあるこの作品。ロックを題材にした漫画では演奏するシーンが重要。
漫画では音は想像で補完するしかないんですが浅野先生がロック好きなのは間違いない。
やはり水色のボディーに鼈甲のピックガードのムスタングですね。
連載当時の00年代だとくるりやチャットモンチー、BUMP OF CHICKEN、フジファブリックの人気がありました。
これらのバンドの共通点は日常をテーマにした楽曲が多いこと。表紙になった多摩川土手の風景もイメージを掻き立てられます。
この頃のバンドが使用しててジャガーやジャズマスターの人気がありました。レミオロメンなんかはファイヤーバード弾いてました。(ちゃんとファイヤーバードの音が出てた)
アジカン
ソラニンの話に戻すと00年代の音楽シーンとムスタングでどんなサウンドかある程度想像できますが映画化もされて曲も演奏されています。イメージどうりでしたか?自分はこれが00年代の空気でこれしかないと思う。
リバーブ効かせてCadd9をジャラーンってくそエモいじゃないですか?芽衣子役の宮崎あおいも素直な歌声で好感が持てます。
アジアンカンフージェネレーションの作曲でアジカンの演奏ではツインギターになってますね。
アジカンが演るとちゃんとアジカンサウンドになるんだけど映画の3ピースのバージョンは芽衣子の最初で最後のステージで演出上少し危うさも漂います。(リズムセクションは安定)
ただそれが泣きのサビで映画のクライマックスを盛り上げています。
映画の演奏シーンで途中から入ってくるオクターブ奏法は天国の種田説あり
Z世代
新装版では各パートの終わりに今の浅野先生の絵で芽衣子や種田が描かれています。
描き下ろしの新エピソードもあってこれが良かった。芽衣子のその後が描かれます。
2000年代に青春を過ごした人たちはゆとりだのZ世代だの呼ばれていますが正直ほっといたれやと思います。
若い頃は大体どの世代も脆弱で不安定。テレビもネットも嘘ばかりで生きる実感は痛みしかないのはわかる。
ただフィクションとはいえソラニンでまず思ったのは
死んだらあかんがな
しんどいけど長生きしたらいいこともあるぞ。と種田に言ってやりたい。
フジファブリック
ソラニンを読んでみてフジファブリックの志村さんのことも重ねてみてしまった。
フジファブリックは僕よりふた回りも下のK君がおススメしてくれて聴くようになりました。”志村日記”なる志村さんのブログをまとめた本も貸してくれました。
“志村日記”には日々の生活のことやレコーディングの進捗などが淡々と綴られているだけ。みんな志村さんが何考えて生きてたのか知りたいんですよね。
地元でのコンサートの志村さんのMCと”茜色の夕日”は胸が潰れる。
フジファブリックをリアルタイムで聴いてた人たちはつきささったままで生きていますが交わることのなかった彼らの気持ちが少しわかったような気がしました。
それはソラニンの芽衣子たちの気持ちにも似ている。僕はK君との触れ合いで彼らの人生を少しだけ横切っただけだけど漫画の背景のように溶け込んでいたらいいなと願う。
ちなみにK君その後上京し結婚して幸せに暮らしています。
バンド漫画としてのソラニン
ロックを題材にした漫画は沢山あります。
BECKやシオリエクスペリエンス、アニメでは”けいおん”なんかですね。
BECKはバンドとしての成功とロックミュージックの本質みたいなものが描かれますがソラニンではどうでしょうか?
うだつの上がらないバンドマンの日常がリアルにダラダラ描かれますがカタルシスはラストのライブ。物語はただこの一点に向かって進んでいきます。
スポーツ漫画と違って勝敗ではなくロックの高揚感や神がかった瞬間が描かれます。
フェスやコンサートに行ったことがある人なら感じたことがあるはず。
若者の怠惰な日常と主要キャラクターの死。それでも続いていく日々。最初で最後のライブでの演奏。
ロックミュージックは構造的に溜めと解放の美学でもあり物語の構成とリンクしている印象があります。
映画ではアジカンの楽曲はハマっていました。ドラムのリムショットとメロディアスなベースラインのヴァース。ブリッジで溜めてコーラス(サビ)で解放。王道っちゃあ王道ですがみんな大好きなやつ。
作者の浅野先生はロックの即効性と無力なところを冷静な視点で見ていたと思います。
物語としてのソラニン
加筆部分を持ってソラニンが完成されたと思っています。種田の死はストーリー展開において実験的な要素もあったとインタビューでおっしゃっています。
ただフィクションとはいえ死を描くにあたって責任感もあったはず。
種田が死の間際、独りごちてるのがすこし綺麗すぎる。(個人の感想デス)
描き下ろしは#28 #29とあり時系列で数年後の話。#28だけサブタイトル”はるよこい”
とあります。
近作の精密な背景とキャラクターで描かれるソラニンのその後。#28で登場する本編には縁のない元恋人同士のふたり。
別れの後 『こんなとき楽器が弾けたなら』 とモノローグで語られます。芽衣子たちの世界と語られない恋人たちの物語が交差します。
土手を歩く彼女のエアギターのジャラーンはきっとCadd9。
浅野作品の魅力
草食系男子のロックが世界系の物語と同時多発的だったかどうかは知らんけど相性はいいはず。
ロックが自己中心的で世界の終わりが主観であるならそれぞれの世界に終わりがあるんですね。
短編”勇者たち”でそのへんはループものへの自嘲も含めてギャグにしています。
精密な背景の中のキャラクターたちはその数だけ世界があり平等に描かれます。
デデデのことで書き忘れたけど”水木しげる”先生の影響がありますね。背景の描き込みや極端にデフォルメされたキャラクター。浅野版”河童の三平”とか面白いかも。
ソラニンは先生が若い頃の熱量が詰まった作品です。勢い余って死んじまった種田ももう許してあげたい。
まとめ
隙あらばadd9弾きがち。
-
前の記事

デデデのこと 2022.04.23
-
次の記事

シン・ウルトラマン の話 2022.05.21