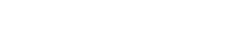メロコアの話
- 2020.04.19
- アーティスト語り
- BRAHMAN, EASTERN YOUTH, Hi-STANDARD, KEMURI, NICOTINE, POTSHOT, SNAIL LAMP, スカコア, バンド, メロコア, 壱ノ盆, 音楽

最近弐ノ盆さんとメロコアの話をすることが多くなってきて、久々に内なるメロコア熱が上がってきました。
洋楽の話は弐ノ盆さんの得意分野なので、今日は邦楽メロコアの話を、バンド少年に向けた主観的なコピーの話もちょっとだけ混ぜながら解説していきます。
メロコアとは
メロディック・ハードコアの略で、日本由来かと思ったら元祖は海外でした。
日本のパンクロックシーンの中で1990年代に人気になってきたパンクロックの1ジャンルって言われていますが、ジャンルの話は難しい。エモいって何?
とりあえずは歪みの効いたメロディアスなギターリフで2ビートで刻むアップテンポな曲をやってたらメロコアでいいんじゃないでしょうかと思うので、勝手に定義して進めます。
Hi-STANDARD
通称ハイスタ。
兎にも角にもまずはこのバンドの話をしないとメロコアの話はできない、ってぐらいの日本でのスーパー第一人者です。
この人たちだけで余裕で1記事できちゃいますが、今日はメロコアの話なのでなんとか簡潔に話さないといけません。
ベースボーカル、ギター、ドラムの3ピース構成で、それまではもう一人ギターがいる、もしくはボーカルは楽器を持たない4人もしくは5人の構成が多かったですが、この3ピースバンド編成も流行りました。
PIZZA OF DEATH RECORDSというインディーズレーベルに所属していて、大手レコード会社に属さないインディーズバンドってのも流行りました。時代の流れですね。
今ではよくある大規模な野外バンドフェスも、国内ではハイスタが主宰したAIR JAMが最初って言われてたりする、とてつもなくその後のバンドに影響を与えた伝説的なバンドです。
一度は解散しましたが、東日本大震災をきっかけに再結成。今リアルタイムでハイスタが見られることはとても幸せなことです。
ということで曲紹介。
ハイスタと言ったらやっぱりこれ。
STAY GOLD
輝いてますかぁ? 輝いちゃってますかぁ?
つねさんのライドシンバルとスネアの早い2ビートドラム。横山健の歪みの効いたメロディックなギター、青臭い歌詞と難波さんのベースボーカル。これぞハイスタ。そしてこれがメロコア。
曲自体は解散前ではかなり後期の曲なのですが、代表曲となっています。
初期時代から良いアルバムが多いですが、この曲が収録されたMAKING THE ROADはハイスタの完成系とも言えるのではないでしょうか。素晴らしいアルバムです。
この曲をコピーしようと思ったら、ベースは割と簡単ですがそれはベースボーカルだからです。弾きながら歌うことに慣れないといけません。
ギターはイントロや間奏でも弾かれているキャッチーなメロディのところが一番難易度が高くて、完璧に弾こうと思ったら結構難しいです。
そこをクリアしたら後は早いカッティングが待っているので、ひたすら練習ですね。
ドラムはとにかく早いです。あと裏からのリズムと表からのリズムが混ざるので、まずはこの早いテンポをどちらからでも叩けるようにならないといけません。
その後に待っているのはつねさんのクセとも言えるバスドラの踏み方。自分は最初かなり苦戦しましたが、これが踏めればハイスタドラムの第一歩がスタートできるので頑張りましょう。
BRAHMAN
メロコア+民族音楽を融合させたバンド。
勝手なイメージだけど、ハイスタが陽ならブラフマンが隠。
MCをしないライブ、シャウトなボーカル、静かさと激しさを混ぜた曲、クールでカッコいいんですよ、このバンドは。
ライブも男臭くて魂ぶつけてるって感じがしてかなりハードコアな部分が強い感じがします。シャウトもラウドっぽいですね。
甲子園でもよく聞くSEE OFFも有名ですが、個人的に一番好きな曲はやっぱりこれ。
DEEP
HEAD WAY!!!
当時のライブハウス、学園祭でカバーをしたものなら必ずHEAD WAY‼︎!って合唱が起きていました。
サビギターではカッティング&ブリッジミュートの連続です。
ブリッジミュートはパンクやロックギターでよく聞くズンズンと響かせる音にする奏法なんですが、ピックを持つ手でブリッジ付近をミュートしながら弾く奏法です。
この曲をコピーしようと思ったらまずはここが弾けるようにならなければなりません。
ベースも結構動くのとドラムもおかずをかなり入れてくるので、初心者バンドはコピーに苦戦するところが出てくると思いますが、弾けたらかなりカッコいいです。
NICOTINE
ニコチンもよく聞いたなぁ。
ハイスタ、ブラフマンと比べるとライブではあまりカバーされていなかった気もするけど、自分は大好きでした。
アルバム買うお金もないので、レンタル屋さんに行ってはCD借りていた時代、懐かしい。
楽曲的には日本の感じよりアメリカンパンクロックに近いんじゃないでしょうか。欧米かっ。
自分はこの曲が好きです。
BLACK FLYS
oh oh, Black Fly、日本語訳だとハエですね。
終わりかたが特徴的だなって思って、下がるんじゃなくて上がるんですよね。カッコいい。
あとツッタンドゥクダン、ツッタンドゥクダン、分かります?スネアどハイハットどバスドラの刻みかたです。
ザ・メロコア王道ドラム。メロコアに限ったことではないけど、2ビートのアップテンポの曲をしたければドラマーはこの叩きかたが登竜門ですね。
二連のバスドラの踏み方に悩んで練習します。そして爪先とかかとで踏むことができるようになったら、テンション上げてあとはリズムを早くしていきましょう。
その他楽器は割と簡単な方だと思います。
ギターソロも結構簡単なので、初心者向けとは言えませんが簡単な曲が弾けるようになったら挑戦してもいい曲だと思います。
POTSHOT
ちょっとメロコアからスカコアって言われるジャンルに移っていきますが、まぁ細かいことはいいじゃないですか。
当時はメロコア&スカコアムーブメントでした。
読み方はそのままポットショットですね。
スカコア、これも流行りましたね。ンチャンチャって裏で刻むカッティングギター、そこにホーン隊が混ざって、イントロやサビでの歪みギター。これが王道スカコアです。
ポットショットは明るくて合唱したくなるような曲が多いです。実際に大合唱ができるようなバンドを目指して結成したらいですし、曲にもWohとかOhとかAhとか多いです。楽しいのはいいことですね。
She is cute
個人的に一番好きな曲はこれ。
アッアッアッアーン、これ合唱ですよね。途中で流れる手拍子も気持ちいい。
全体的にこの時代のバンドの曲は短い曲が多いいのと、大きく展開が変わらないのでバンド少年たちはコピーはしやすいですよね。
ただしスカコアをやる上で一番の難関、それはホーン隊の確保です。
ホーン隊は吹奏楽部からの勧誘、これ鉄板でした。
KEMURI
こちらもスカコアバンドの大御所。
結成当初からケムリは海外での活動が多いってイメージがありますが、ハイスタもそうだけど、しょっぱなから海外に挑戦って凄いなって思います。
ケムリはこの曲を紹介。
Ato-Ichinen
あと一年、あと一年!
キャッチーですよね。母さんの手を握りしめって聞こえた瞬間、当時の壱ノ盆少年は日本語だ!ってなった覚えがあります。
当時みんな英詞ばっかだったので、日本語に新鮮さを覚えると言う謎現象が起きていました。
ボーカル伊藤さんの歌いかた、滑舌良い訳ではないですしクセのある歌いかたなんですが、意外に聞き取りやすいでんすよね。
伊藤さんが参加したスカパラとのコラボ曲、Pride Of Lionsもお勧め。一番の聴きどころはアウトロの展開なんですけどね。
この曲もコピーをするには、まずは吹奏楽部の人を説得しましょう。
そしてギターの人はスカの特徴でもある裏でのンチャンチャっていうカッティングの練習が必要です。
ピックを持つ方の手でダウンピッキングの時に手の小指の下の面(空手チョップをする面ね)を弦に当ててミュートします。
あとはアップピッキングの時に二弦ぐらいまでチャって鳴らす感覚を掴んで、更にリズムを早くしていけばそれがスカコアカッティングです。
SNAIL LAMP
スネイルランプ。
こちらはスカコアですがホーン隊のいない3ピースバンド編成で、いわゆるスカコアバンドよりはスカ要素は薄くなりますが、その分メロコア要素が強いイメージです。
当時のインディーズバンドはテレビに出ない印象、もといそれが暗黙のルールなのかなって思ってましたが、HEY!HEY!HEY!だかに出てた時におおっ!とうとうテレビに出る時代になったのかって驚いた思い出があります。
ベースボーカルの竹村さんがやっていたオールナイトニッポンで、一発屋の話題になったときに竹村さんが言った言葉、
“文句があるなら一発売れてみろ、一発売れるのがどれだけ大変か”
って言葉がすごい印象に残っています。
スネイルランプといったらこの曲でしょう。
MIND YOUR STEP
この曲は流行りましたね。イントロから痛快なギターが流れます。
ベース弾きながら歌うの難しいんですよこれ。よくできるなって思います。
スネイルランプはギターもちょこちょこ遊び入れてくるので、初心者バンドがコピーするのはちょっと難易度高めな気がします。
間奏でギターがやるブリッジミュートとオクターブ操法の連続と、ギターソロ最後のスライド&ハンマリング・プリングの連続は結構練習した思い出があります。
ドラムのスネアの刻みかたといい、ちょっとベンチャーズっぽいところがありますね。
カップリングのGOING TO CANGEもとてもいい曲。
EASTERN YOUTH
イースタンユース。
ちょっと男子ぃ、イースタンユースはメロコアじゃなくてエモコアでしょ?って言う方すみません、正直もうよく分からん。
たしかに少しズレますが単純に大好きで記事を書きたかった。ハイスタとイースタンユースはいつかそれだけで記事にしたいなぁ。
このバンドはやはりその強烈なビジュアルと、強烈なシャウトと、強烈なギターサウンドと、ゴリゴリ(ブリブリ)のメロディックベースが特徴的です。
最初はゴリゴリのパンクバンドでタイトルも英題だったんですが、いつからか今のメロディックで激しさの中にも多彩な音楽性を併せ持ったバンドになっていきました。
イースタンユースはこの曲。
夏の日の午後
熱いですね!ギターソロ後のシャウトが最高に熱いです。
そして滲み出るおじさん感、焼酎感!いいですね。
各パートそれぞれしっかりとした技術があるのですが、個人的に凄いと思うのがベース。
どの曲もベースがブリッブリに動きまくってて難しいのに、淡々と弾く感じ、好きなんですよ。
ギターは歌いながら弾いているのもありイースタンユースの中では割と簡単なパートだと思いますが、しっかりとリズムキープしながら歌う練習が必要です。
ベースは先述したようにかなり動くので覚えるのが大変なのと、動きながらもしっかりと粒の揃った音を出すのは苦戦すると思います。
ドラムは難しいです。スネアが決めてだと思いますが、強めのインパクトとロールが入る曲も多いので、ロールの練習が必要です。
決めのブレークも多いのでしっかりと止めるところは止める、といった色々なテクニックがいりますね。
自分もまだちゃんとロールできないので、練習しないと。
まとめ
バンド少年たちよ、90年代のメロコアも良いんだよ。
-
前の記事

FIVE STAR STORIESの話 2020.04.12
-
次の記事

パンクの話 2020.04.26